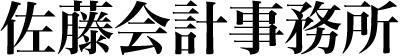01法人サービス
税理士の変更をご希望の方
- 税理士がなかなか訪問してくれない
- 試算表や決算書がなかなか出てこない
- 節税のアドバイスがもらえない
- 記帳代行ばかりで経営のアドバイスがもらえない
- 年齢が離れていて話が合わない
- 税務署の味方をする
- 上から目線で相談しにくい
- 税法の知識に不安がある
今の税理士にこのような不満はございませんか?
資格試験が重視される昨今では税理士の数も多くなり、税理士を変更することは決して珍しい時代ではなくなってきました。
佐藤会計事務所では、勉強熱心な若い税理士が多数在籍しています。フットワークが軽く、遠方でも毎月訪問させていただいております。また、毎週月曜日の朝に勉強会を行い、日々新たな知識の習得に取り組んでおります。
必ずあなたの理想の税理士に出会えることを約束します。